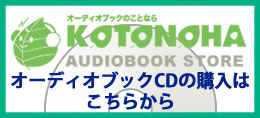☆☆☆☆☆☆
==================================================================
【 ことのは出版 連絡帳 】 vol.28配信日:2009年3月20日
==================================================================
☆☆☆☆☆☆
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
※ 本メールアドレスは配信専用です。
※ 本メールはことのは出版の活動を通じて得た皆様のメールアドレスに配信させ
ていただいています。メルマガ解除の方法は最後の部分をご覧ください。
※ ことのは出版HPはこちらです。画像にも自信あり!一見の価値在り、のはず。
http://www.kotonoha.co.jp/
==================================================================
●CONTENTS
1:ご挨拶。
2:それはニュースだ!
3:新刊だ!新刊だ!!
4:これもオススメですよ?
5:中華風。
6:イベント紹介。
7:余談。
==================================================================
●1:ご挨拶。
==================================================================
ある朝のこと。ほげほげ~と新聞を繰り、チラシに目を通しておりましたとき、カルチャー教室のチラシに目がとまりました。「シャンパン入門」やら「宇宙食をつまもう」やら最近のカルチャーってすげえ☆とおもしろくながめておりましたころ・・わーかーほりっくのワタクシ、あることに気づいてしまいました。朗読の教室が多い!!!数えてみたら9種類、発声・声で表現といったものも含むと12種類!!!
皆さん、時代は朗読ですよ!
と、いうことはオーディオブック時代ですね!
==================================================================
●2:それはニュースだ!
==================================================================
■来月発売の印刷業会向け雑誌「プリバリ 印」にオーディオブック関連の記事が掲載されます。
社団法人日本印刷技術協会(略称・JAGAT、ジャガット:Japan Association of Graphic Arts Technology)が今年から発刊された「プリバリ 印」という雑誌にて(http://www.jagat.jp/content/view/351/192/ )
大日本印刷の池田 敬二様が連載コラムでオーディオブックについて取り上げるというご連絡をいただきました。
この雑誌コンセプトにあるとおり<多様な情報媒体がクロスするなか、印刷メディアは、新たな時代における価値を創る、積極的な対応を求められています。「プリバリ 印」は、ビジネスシーンに直結する新たな印刷のカタチ、表現、効果など新しい価値創造の可能性を提案していきます。>と非常に前向きな業界誌です。
そのなかオーディオブック業界の人が書くのではなく近しい業界から見た市場考察ということで記事は非常に楽しみにしています。単体での購入もできますので、興味のある方は是非。
最近指摘を受けているのがオーディオブックを「科学」として話すことができる研究者がいない。ということをききます。パブリックな場でオーディオブックを話すために例えばことのは出版の誰それを呼んでも自社のビジネスモデルの話しかならない。
普通、どんなニッチなカテゴリでもその道の達人(研究者)というのはいるのが普通ですが、日本ではまだオーディオブック研究者は見あたらない・・・。(チャンスですよ)
そういった意味では今回の「プリバリ 印」は初めての「科学」(考察)寄りの記事になるかもしれません。
私も時間を見つけては「科学」としてのオーディオブックを勉強したいと思います。
目指せ!「オーディオブックの文化人類学」「オーディオブックのフォークロア」「オーディオブックの社会学」!
==================================================================
●3:新刊だ!新刊だ!!
==================================================================
新刊発売され・・・てません。
フキョーですからね!ジャクショー企業にはそんなにぽんぽこ出せないのですよ!
でも、大丈夫☆ 今までの積み重ねがありますから。コンプリートしようとしたら結構たいへんです。頑張ってください!!(←本気ですっ)
★イッパイアルヨアルヨ~→http://www.kotonoha.co.jp/title/index.html
★そのなかでも新しいのは→http://www.kotonoha.co.jp/title/jidai/kunoiti2.html
==================================================================
●4:これもオススメですよ?
==================================================================
○桜の樹の下には 著 :梶井 基次郎
朗読:今泉 孝太郎
春です!
花粉です!
ワタクシはまだ花粉リミットを迎えていないのですが、いざそのときを迎えてしまったら、お花見はどうしたらよいのでしょう。夜ならまだましだそうですが、快晴の下で花がこぼれてくる枝を見上げるのはまた格別ですから。――それに。それに、夜桜はこわいですよ、死体が起きあがって来ちゃったら・・!!
さて。
ここで何故死体?と思う方はこちらをどうぞ。
お花見の肴にも。目は、花を見るのでおおいそがしでしょうから。
大丈夫です、桜に、おさおさ見劣りしないです。
「桜の樹の下には屍体が埋まっている! これは信じていいことなんだよ・・・・・・・」
==================================================================
●5:中華風。
==================================================================
「評書」。中国の講談のようなものだそうです。
ネット普及が追い風となり、毎日のように聴いているひとが1億人をかぞえるとか。中国語は土地ごとにまったく発音が違いますから、その土地土地の評書があるのでしょうか? 中国人は評書によって三国志や水滸伝をしり、歴史上の人物をしるとも。 ・・・しかし、劉備、ときいて「三国無双(ゲーム)」のキャラクターですね、と言った中国人も本当におられるようですし、ひそかにファンの高齢化がすすんでいるのかもしれません。
ネット&オーディオブック文化パワーでおしもどしていただきたいところです。
それにしても、こういう下地があるのなら、かの地でのオーディオブックの普及は予想以上に早いかもしれませんね。
==================================================================
●6:イベント紹介。
==================================================================
☆2010年国民読書年に向けて視覚障害者・高齢者の読書バリアフリーを考えるシンポジウム
2010年って国民読書念だったのですね。
・・・・・
・・・・・
いえ、つっこみどころはそこではありませんね。はい。
「読書バリアフリー法」の制定を目指して、活字を理解しづらいひとの権利を論じたり、よりよいサービスを考えたりする為の催しがおこなわれます。
病院代は値上がり、年金受取口だった近所の郵便局は閉まり、福祉予算は削られるなか、本なんか読まなくても死にゃしませんが、人はパンのみにて生きるにあらず。どんな境遇であれ空想や思考の世界くらいは自由自在に味わえるようでありたいものです。新聞や広報といったものになると現実世界の有利不利にも影響してきますしね。
日 時: 2009年3月21日(土) 13時~16時30分
場 所: 日本盲人福祉センター(新宿区西早稲田2-18-2 電話 03-3200-0011
地下鉄副都心線 西早稲田駅 出口1からおよそ徒歩3分
問い合わせ・申し込み先
バリアフリー資料リソースセンター(BRC)事務局
〒171-0031 東京都豊島区目白3-21-6-101
電話03-3950-5260 ファックス03-5988-9161 電子メールinfo@dokusho.org
※Eメール、FAX、郵便などでお申し込みください。
点字・拡大文字・テキストファイルでの資料の用意してくださるそうです。
==================================================================
●7:余談。
==================================================================
先日、はたらく女性について研究してオラレル方にお会いする機会がありました。
その方は、働く女性を集めて意見をずいぶん集めておいでなのですが、近ごろ「今後も働きたい・子供なし」の女性に子供はつくらないのか訊くと口裏を合わせたかのように「無理」と言うそうです。残念なことだ、とずいぶん嘆いておられましたが、無理ないことだと思います。
ここを読んでくださっている男性がもしいらっしゃったら、男手ひとつで今の仕事をこなしながら子育てできるか考えてみてください。
極端かもしれませんが、働く女性は出産するときほぼそういう状況を覚悟せざるをえないだろうと思うのです。法律も制度も、そう手厚く守ってはくれませんし。
==================================================================
読者の皆さんからのご意見・ご感想・ご質問などをお待ちしています!
メールアドレスはこちら → kansou@kotonoha.co.jp
メルマガの配信登録・停止はこちら ↓
http://www.kotonoha.co.jp/maga/mailmagajin.cgi
==================================================================
☆~★ 4月前半は1日配信予定ですまたお会いしましょう~ (^0^)/ ~★~☆
発行元:ことのは出版 http://www.kotonoha.co.jp
==================================================================