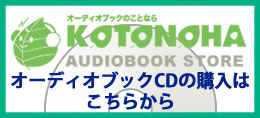オーディオブックの読みは書道と似ているかもしれません。
何か禅問答のような問いかけから始まりましたが、色々な意味で共通項があるなあと感じています。
■臨書に通じるもの
書道を始めるときはまず、臨書(お手本を元に忠実に再現する)で、筆の使い方、楷書なら楷書の基礎を書いて書いて覚えていきます。そうすると自然と適した姿勢、筆の持ち方が身につきます。
オーディオブックも同様に基礎となる発声と音程、アクセント、リズム感を音読しながら型を作ります。
ひたすら声を出して。そして理想はマイク前でその練習を行うことです。
マイクはデジタル信号に変換されますので、自分の声がどのように変換されるか?聴こえるか? そこの把握がスタートになります。
基礎も無しに表現に走ると書道ではただの落書き、オーディオブックも不快な音源にしかなりません。
最近は合成音声の声をあちこちで聞きますが、違和感あると思いません? それは基礎のどれかが抜けているからです。
マイク前で基礎の型を表現できるようになる。それだけでもナレーターとしてやっていけます。
その中で何十時間、何百時間の収録を通して、自分の声の特性にあった、読みやすい話し方が出てきます。それが個性です。
なのでマイクテストや経験の浅いうちは基礎をきちんとマイクに出す。しかも安定的、持続的に! これができる人がオーディオブックナレーションで食べていける人になります。
■起筆 送筆 収筆
書道では書き始めの起筆、書いている途中の送筆 そしてトメ、払いなどの収筆が書き方の基本ですが
オーディオブックナレーションも似たような性質があると思っています。
起こす、流す、止める。これができるひとのなんと少ないか?
起筆に当たる所は、文章の最初の声のあて方、入り方です。
例えば「今日は晴れだった。」という文を読むときに
今日は晴れだった。 と今日に強いテンション持っていかないですよね。
しかし・・・
めちゃくちゃその例は多いです。頭だかで入る人はものすごく多いです。
出だしのところでブレス余裕あるせいか、高く入ること頻繁にあります。
ブレスを一定量で読み続ける型を身に着けないと。途中の「晴れ」あたりでよれ始めて、だった。でブレス切れつつすぐに次の文章に無理やり入って行こうとする。オーディオブックかなりの経験者でもつい出がちな要素です。
一文を起こす(その際に高く入るのか?低く入るのか?平板ではいるのか?)、一定のブレス量でブレずに流す、そして語尾ではしっかり止める。そして次の文もまた起こす、流す、止める。これが基本だと思います。
特に止める。文章では である。 だった。などが多いですが送筆の流れをトメずに収筆(収音)にはいると、最後の「である」のRの音や 「だった」のTの音が出せないだらっとした読みになります。
それでなくてもRや子音のTはマイクを通すと難しい音なので、特に目立ちます。
オーディオブックのナレーションにかぎらず、他の声の読みでも、読み上げは書道だ!一文一文集中、そして慣れてきたらその先にある文意を把握して、この文は立てるべきところなのか、流すべきところなのかを把握できるようになれば、作品全体の起筆、送筆、収筆にあたる読みができるようになると思います。
是非、文章はなんでも構いませんので、ブレスは一定(強弱はいりません、マイクは強弱は単にゲインとしか捉えてくれません)音階の高低で文章を読み。そして収める(しっかり止める)という練習をしてみてはいかがでしょうか?